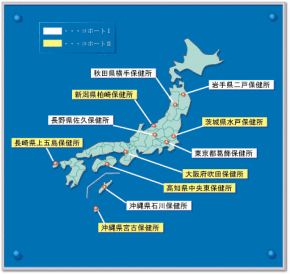一方人類はこれまで、木材からはじまり、石炭、石油など化石燃料へとあらゆるものを燃やしてエネルギーを取り出しその結果、大気中に二酸化炭素を大量に排出してきました。いまこれを逆にギアチェンジするともいうべき新技術が登場しつつあります。植物が行なっている、水と二酸化炭素を材料とし、有機物と酸素を生産するという「人工光合成」の技術です。
植物は、最初に水を分解して水素を作り、それと二酸化炭素を反応させて有機物を作っていることがつきとめられました(驚くべきことにこれは比較的最近分かった事実です)。これを技術で再現できると考え、いま世界中で精力的な研究開発が進められています。多くは反応を効率的にする触媒の開発です。大気中の窒素を固定する化学反応以来、あるいはそれ以上の技術革新と言える二酸化炭素から有機物を生産するという新技術は、はたして確立できるのかいま世界中が注目していると言っていいでしょう。
前回述べた「オオシャコガイ」の体に共生している「褐藻類」は、光合成で有機物を作り出しています。物質の収支で見ると、一個の個体が、水中から二酸化炭素を取り込みそして呼吸でそれを排出するという特殊な生き物といえます。人類もこれに倣い、一方的な二酸化炭素の排出の時代から二酸化炭素を逆循環させ活用する時代へと進んでほしいものです。