がん、心疾患、脳卒中(脳こうそく、クモ膜下出血など)というのが長らく日本人の3大死因でしたが、近年脳卒中を抜いて「肺炎」が第3位となって(2011年)注目されています。肺炎の増加はいまも続いており、毎年11万人の日本人の命を奪っていると言わられいます。この背景にあるのは、後期高齢者の増加とそれに伴う「誤嚥性肺炎」患者の急増が疑われます。
誤嚥性とは、本来喉から食道に行くべき食べ物や唾液が、誤って気道に入り込み、食べ物や唾液に含まれている菌(肺炎球菌、インフルエンザ菌、黄色ブドウ球菌など)あるいはウイルスが肺に至り炎症を起こす病気です。なぜ誤嚥を起こすようになるのか、実は様々な要因があり未解明なところも多いのですが、呼吸器科、耳鼻咽喉科、歯科、リハビリ栄養学など関連する多様な専門家が強い危機意識をもって予防や治療への取り組みがはじまっています。そもそも飲み込むという動作は、想像以上に複雑で喉に空気が入ってくるときは気管は開いていますが、一旦固体や液体が入ってくると喉の筋肉や神経が連動して瞬時に気管の蓋(軟口蓋)が閉じられます。この動作は「嚥下反射」と呼ばれるものですが、加齢とともにこの反射は弱く、あるいは鈍くなり閉じるのが遅れるようになることがあります。誤嚥はこうしたことが原因で起こりますが、食事中にむせやすくなってきたなどは要注意といわれています。こうした「喉の虚弱化」が、命を奪う病気のはじまりとなるのです。誰にでもやがて訪れる「嚥下機能」の低下、いまあらためて目を向ける必要がありそうです。
2017年11月22日水曜日
2017年11月10日金曜日
のどが衰えるとフレイルが加速される!?
高齢社会において大切なテーマとして、はたして老化とは何か、あるいは加齢によりヒトのからだに何が起こっているのかという課題に関心が集まっています。その解明のひとつとして「フレイル」という概念と定義が生まれてきました。この概念は、日本語で言うとこれまで「虚弱」と呼ばれてきたものだと言われていますが、体力の低下や、筋肉の衰弱、反射神経の低下などからだの総合的な機能低下を考えようとするものと理解できます。老化は足腰からとか、口腔からとか議論されていますがもうひとつ忘れてはならない部位に「のど」があります。高齢者の衰弱が進む理由に「嚥下障害」が指摘されています。脳卒中などが原因でこの障害が発症しますが、加齢による嚥下力の機能低下は深刻で今後の重要なテーマになると予想されています。医療の現場では嚥下障害はコモンディジーズ、つまりだれでも発症する可能性のある症状とされています。のどでごっくんとやってみるとわかるのですが、食べ物や水を飲み込むとき「のどぼとけ」がぐっと上に上がり、ようやく飲み込めることがわかります。のどは、呼吸や発声する場所でもあり、食道につながる部位でもあるというように何役もこなす非常に大切なところですが、普段見えないのでそれほど意識することはありません。のどの働きのメカニズムは非常に繊細で、びっくりするほどの作業を行っています。つまり空気を入れたり、食塊を入れたりするためのきわどい調整を行っています。のどの反射神経や、筋肉が衰えてくると何がおこるのか、それは想像を超えて虚弱への道となるのです。
2017年8月22日火曜日
光を吸収も放出もしない!謎の物質「ダークマター」とは?
宇宙に関する知識や考え方が歴史的な大展開をみせています。わくわくする科学分野を挙げるとすれば、それはまちがいなく天文学や宇宙論と言えるでしょう。
私たちが知っている素粒子、原子ではない“物質” らしきものとして「ダークマター」あるいは「ダークマター粒子」が大宇宙に存在することは、すでに決定的となっています。遠く離れた私たちの天の川銀河とは異なる銀河。そのなかでも渦巻銀河の精緻な観測から、ある事実が浮かび上がってきました。銀河系は何億年という悠久の時間をかけて公転していますが、銀河の中心からどれだけ離れた恒星も同じ公転速度であることがわかってきました。この銀河の回転速度で飛び出そうとする力を留めているのは、銀河全体の総重力と考えられますが、恒星の総量を合わせても計算上これを引き留める物質量にはならないといいます。そこには何か恒星が飛び出すのをつなぎとめる「引力」が必要となりますが、この引力を生み出しているものこそ見えない物質「ダークマター」だとされました。
また銀河系がレンズとなって光を曲げる現象でも、このダークマターを計算にいれないとつじつまがあわない光の偏向があるといいます。そしてふたつの銀河が衝突し、合体したと思われる「弾丸銀河団」ではこの不思議な物質は、相互に影響することなく銀河団をくぐり抜けて、まるでミッキーマウスの耳のような球状の構造を作っているとされ、だれもがこの「見えない物質」がどうやら銀河の構造を形作っているようだと信じるようになりました。電荷をもたず、光を吸収も放出もしないというダークマター粒子、それはいったい何者なのでしょうか。研究者たちは、このダークマターは、銀河系にとりつくように大規模の構造体を形成しており、銀河系の構造はどうやらダークマターが決めていると考えています。
弾丸銀河団
私たちが知っている素粒子、原子ではない“物質” らしきものとして「ダークマター」あるいは「ダークマター粒子」が大宇宙に存在することは、すでに決定的となっています。遠く離れた私たちの天の川銀河とは異なる銀河。そのなかでも渦巻銀河の精緻な観測から、ある事実が浮かび上がってきました。銀河系は何億年という悠久の時間をかけて公転していますが、銀河の中心からどれだけ離れた恒星も同じ公転速度であることがわかってきました。この銀河の回転速度で飛び出そうとする力を留めているのは、銀河全体の総重力と考えられますが、恒星の総量を合わせても計算上これを引き留める物質量にはならないといいます。そこには何か恒星が飛び出すのをつなぎとめる「引力」が必要となりますが、この引力を生み出しているものこそ見えない物質「ダークマター」だとされました。
また銀河系がレンズとなって光を曲げる現象でも、このダークマターを計算にいれないとつじつまがあわない光の偏向があるといいます。そしてふたつの銀河が衝突し、合体したと思われる「弾丸銀河団」ではこの不思議な物質は、相互に影響することなく銀河団をくぐり抜けて、まるでミッキーマウスの耳のような球状の構造を作っているとされ、だれもがこの「見えない物質」がどうやら銀河の構造を形作っているようだと信じるようになりました。電荷をもたず、光を吸収も放出もしないというダークマター粒子、それはいったい何者なのでしょうか。研究者たちは、このダークマターは、銀河系にとりつくように大規模の構造体を形成しており、銀河系の構造はどうやらダークマターが決めていると考えています。
弾丸銀河団
2017年7月26日水曜日
赤い太陽系の惑星に酸素を探す~われわれはもう孤独ではない?!~
地球サイズの惑星が7つもあり、その内の3つは水が液体で存在できると考えられている、水瓶座の方向へ40光年先(とても近い!)にある赤い太陽系(赤色矮星と惑星群)「トラピストー1」にいま大きな関心が集まっています。
セブンシスターズ(7姉妹)と呼ばれている新たに見つかった「系外惑星群」は、大きさがどれも地球サイズで、しかもどれも「岩石惑星」であることから、これまで人類が長らく夢見てきた、この宇宙のどこかにある、もうひとつの地球という夢想にひとつの答えを出すものとなる。SFのおとぎ話であったこんな地球型惑星が、科学の話題として議論される時代になったとは、誰が予想していたでしょうか。
はたしてこれら惑星群には、大気はあるのでしょうか。もしあるとすればその組成はどうなっているのでしょう?大気に生命の存在を示す「酸素」ははたして存在しているのでしょうか?水は存在しているのでしょうか。興味の尽きない研究課題が次々と解明を待っており、いま世界中の天文台では、熱い大気観測合戦が繰り広げられているとのことです。
しかしもし、酸素が大量に存在することが観測でき、水も液体であるというという答えが出てきたとき、この科学的事実の重さは、計り知れないものがあり、衝撃的といっていいのではないでしょうか。「生命」とは何か、われわれはどこから来てどこに行くのか。画家ポール・ゴーギャンも問いかけた、宇宙に中での命の意味を再びわれわれに突きつけることとなるでしょう。地球型の生命がこの宇宙には、どこでも存在する可能性がもし明確となったとき、人類の自然観や宗教観など根底からひっくり返される可能性があります。
わくわくするのは、この系外惑星群の組成解明は科学的に可能であり、実にすぐそこに迫っているということです。小さな地球で、たったひとつの生命、DNA型の生命しか知らなかった私たちですが、大宇宙がなぜ生命を生んだのか、わたしたちの存在とは何なのか、その答えのひとつがいま解き明かされようとしているのでです。
セブンシスターズ(7姉妹)と呼ばれている新たに見つかった「系外惑星群」は、大きさがどれも地球サイズで、しかもどれも「岩石惑星」であることから、これまで人類が長らく夢見てきた、この宇宙のどこかにある、もうひとつの地球という夢想にひとつの答えを出すものとなる。SFのおとぎ話であったこんな地球型惑星が、科学の話題として議論される時代になったとは、誰が予想していたでしょうか。
はたしてこれら惑星群には、大気はあるのでしょうか。もしあるとすればその組成はどうなっているのでしょう?大気に生命の存在を示す「酸素」ははたして存在しているのでしょうか?水は存在しているのでしょうか。興味の尽きない研究課題が次々と解明を待っており、いま世界中の天文台では、熱い大気観測合戦が繰り広げられているとのことです。
しかしもし、酸素が大量に存在することが観測でき、水も液体であるというという答えが出てきたとき、この科学的事実の重さは、計り知れないものがあり、衝撃的といっていいのではないでしょうか。「生命」とは何か、われわれはどこから来てどこに行くのか。画家ポール・ゴーギャンも問いかけた、宇宙に中での命の意味を再びわれわれに突きつけることとなるでしょう。地球型の生命がこの宇宙には、どこでも存在する可能性がもし明確となったとき、人類の自然観や宗教観など根底からひっくり返される可能性があります。
わくわくするのは、この系外惑星群の組成解明は科学的に可能であり、実にすぐそこに迫っているということです。小さな地球で、たったひとつの生命、DNA型の生命しか知らなかった私たちですが、大宇宙がなぜ生命を生んだのか、わたしたちの存在とは何なのか、その答えのひとつがいま解き明かされようとしているのでです。
2017年6月20日火曜日
二酸化炭素を逆循環!人工光合成の技術に人類の期待
海洋に棲息する海藻類、植物性プランクトン、そして地上の植物は、二酸化炭素と水を原料として、太陽光をエネルギー源として有機物を生産し、酸素を「廃棄物」として排出するという「奇跡のシステム」を30憶年に渡って稼働させてきました。地球大気に酸素が大量に含まれているのは、光合成を行なう小さな生きものたちがずっと酸素を吐き出していたからとされています。
一方人類はこれまで、木材からはじまり、石炭、石油など化石燃料へとあらゆるものを燃やしてエネルギーを取り出しその結果、大気中に二酸化炭素を大量に排出してきました。いまこれを逆にギアチェンジするともいうべき新技術が登場しつつあります。植物が行なっている、水と二酸化炭素を材料とし、有機物と酸素を生産するという「人工光合成」の技術です。
植物は、最初に水を分解して水素を作り、それと二酸化炭素を反応させて有機物を作っていることがつきとめられました(驚くべきことにこれは比較的最近分かった事実です)。これを技術で再現できると考え、いま世界中で精力的な研究開発が進められています。多くは反応を効率的にする触媒の開発です。大気中の窒素を固定する化学反応以来、あるいはそれ以上の技術革新と言える二酸化炭素から有機物を生産するという新技術は、はたして確立できるのかいま世界中が注目していると言っていいでしょう。
前回述べた「オオシャコガイ」の体に共生している「褐藻類」は、光合成で有機物を作り出しています。物質の収支で見ると、一個の個体が、水中から二酸化炭素を取り込みそして呼吸でそれを排出するという特殊な生き物といえます。人類もこれに倣い、一方的な二酸化炭素の排出の時代から二酸化炭素を逆循環させ活用する時代へと進んでほしいものです。

一方人類はこれまで、木材からはじまり、石炭、石油など化石燃料へとあらゆるものを燃やしてエネルギーを取り出しその結果、大気中に二酸化炭素を大量に排出してきました。いまこれを逆にギアチェンジするともいうべき新技術が登場しつつあります。植物が行なっている、水と二酸化炭素を材料とし、有機物と酸素を生産するという「人工光合成」の技術です。
植物は、最初に水を分解して水素を作り、それと二酸化炭素を反応させて有機物を作っていることがつきとめられました(驚くべきことにこれは比較的最近分かった事実です)。これを技術で再現できると考え、いま世界中で精力的な研究開発が進められています。多くは反応を効率的にする触媒の開発です。大気中の窒素を固定する化学反応以来、あるいはそれ以上の技術革新と言える二酸化炭素から有機物を生産するという新技術は、はたして確立できるのかいま世界中が注目していると言っていいでしょう。
前回述べた「オオシャコガイ」の体に共生している「褐藻類」は、光合成で有機物を作り出しています。物質の収支で見ると、一個の個体が、水中から二酸化炭素を取り込みそして呼吸でそれを排出するという特殊な生き物といえます。人類もこれに倣い、一方的な二酸化炭素の排出の時代から二酸化炭素を逆循環させ活用する時代へと進んでほしいものです。
2017年6月6日火曜日
失われる貴重な海の生物種~南シナ海のオオシャコガイを救え!~
地球上で最大の貝である「オオシャコガイ」。泳いでいる人が足をとられて溺れたといった逸話が多く語られてきました。成長した個体は、体長が2メートル近く、重さは200キロを超えるといいます。ニ南太平洋から、インド洋にかけた暖かな海域に棲息しています。貝柱は食用となり、殻は生活道具に利用されたりしますが、真珠を採取できることもあるといいます。
海洋に進出する中国が、南シナ海での領有権争いの末、人工島などの建設でで岩礁の乱開発が進行していますが、環境破壊と生態系への取り返しのつかない破壊行為として憂慮する声が上がっています。米・マイアミ大学の海洋生物学者のジョン・マクナマス博士らはこのままいくと何百という生物種が短期間のうちに絶滅することになると、いま警告を発しています。
スプラトリー諸島での軍事施設(人工島)の建設だけでなく、中国漁師による大規模な密猟も生物に破滅的な影響を及ぼしているといいます。希少なサンゴやオオシャコガイの密猟です。オオシャコガイ漁は岩礁に深く身を沈めるように棲息している生物ですので、これを採取するには岩礁を掘り返しすことになります。つまり岩礁は大きく破壊されるのです。海の中では、岩礁は特別な生態系を生み出す場所で、小さな生物、藻類、また魚の稚魚などがここをは住処としています。こうした多彩な岩礁性動物がを失われると、やがて生態系システムのメカニズムで、これを餌としている大型魚も減少していくのです。
この巨大貝には大きく育つことが可能となる秘密があります。カラフルな貝の体には細胞内に数十億の藻類(褐虫藻)が共生しており、この藻類が光合成で生み出す糖やタンパク質を貝に供給してくれます。こうして労せずに、貝は大きく育つことが可能となったのです。別名「光を食べる貝」と呼ばれる訳はそこにあります。まことに不思議な生き物と言えるのではないでしょうか。もちろん他にプランクトンもロートで濾して食べます。こうして栄養の乏しい海域でも、何億年も彼らはたくましく生き延びてきました。いままた人間の身勝手な行動が、数億年にわたって命を紡いできた貴重な海の生物種にさえ手をかけて、彼らを絶滅に縁に追いやろうとしています。
 写真:ナショナルジオグラフィックス 撮影:George Grall
写真:ナショナルジオグラフィックス 撮影:George Grall
海洋に進出する中国が、南シナ海での領有権争いの末、人工島などの建設でで岩礁の乱開発が進行していますが、環境破壊と生態系への取り返しのつかない破壊行為として憂慮する声が上がっています。米・マイアミ大学の海洋生物学者のジョン・マクナマス博士らはこのままいくと何百という生物種が短期間のうちに絶滅することになると、いま警告を発しています。
スプラトリー諸島での軍事施設(人工島)の建設だけでなく、中国漁師による大規模な密猟も生物に破滅的な影響を及ぼしているといいます。希少なサンゴやオオシャコガイの密猟です。オオシャコガイ漁は岩礁に深く身を沈めるように棲息している生物ですので、これを採取するには岩礁を掘り返しすことになります。つまり岩礁は大きく破壊されるのです。海の中では、岩礁は特別な生態系を生み出す場所で、小さな生物、藻類、また魚の稚魚などがここをは住処としています。こうした多彩な岩礁性動物がを失われると、やがて生態系システムのメカニズムで、これを餌としている大型魚も減少していくのです。
この巨大貝には大きく育つことが可能となる秘密があります。カラフルな貝の体には細胞内に数十億の藻類(褐虫藻)が共生しており、この藻類が光合成で生み出す糖やタンパク質を貝に供給してくれます。こうして労せずに、貝は大きく育つことが可能となったのです。別名「光を食べる貝」と呼ばれる訳はそこにあります。まことに不思議な生き物と言えるのではないでしょうか。もちろん他にプランクトンもロートで濾して食べます。こうして栄養の乏しい海域でも、何億年も彼らはたくましく生き延びてきました。いままた人間の身勝手な行動が、数億年にわたって命を紡いできた貴重な海の生物種にさえ手をかけて、彼らを絶滅に縁に追いやろうとしています。
 写真:ナショナルジオグラフィックス 撮影:George Grall
写真:ナショナルジオグラフィックス 撮影:George Grall2017年6月1日木曜日
適切な肉・乳製品・コーヒーの摂取は健康長寿への道
肉や乳製品を多くとる欧米型と呼ばれる食事を好む方には、朗報かもしれませんが国立がんセンターが主導した大規模な国民追跡調査で何と、「欧米型の食事パターン」を繰り返していた方は、がん死亡、循環器疾患、心疾患(脳血管疾患もやや低下の傾向)、そして全死亡でもそのリスクが低下していた(およそ1割程度)といいます。
なにしろ全国8万人を22年間も追いかけた調査ですので、データの信頼度は各段に高いものと考えられえます。この結果をどう分析するかは今後まだまだ議論を呼ぶものと思いますが、調査を行った国立国際医療研究センターの溝上疫学・予防研究部長らによると欧米型の食事では、塩分摂取が比較的少なく、たんぱく源が適切に摂られている(欧米諸国民ほど肉は大量に食べていないこと)、コーヒーなどもプラスの効果があったからと考えています。肉や乳製品の健康との関係を考えさせられる結果となりました。
では私たちはこれからどういう食事を摂っていくべきなのでしょうか、研究者には健康長寿の視点で、肉や乳製品の摂取のめやすなどをわかりやすく示してほしいものです。高齢者のアルブミン値が低下してる傾向などを考えるときどういう風に肉を食べ、乳製品をどういう風にうまく取り入れるかなども管理栄養士ともども国民に提示してほしい。
こうした生の情報で人々が混乱し、間違った判断をしないためにはそうしたフォローが必要かと思います。
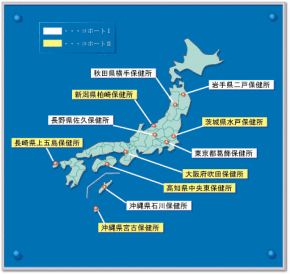
なにしろ全国8万人を22年間も追いかけた調査ですので、データの信頼度は各段に高いものと考えられえます。この結果をどう分析するかは今後まだまだ議論を呼ぶものと思いますが、調査を行った国立国際医療研究センターの溝上疫学・予防研究部長らによると欧米型の食事では、塩分摂取が比較的少なく、たんぱく源が適切に摂られている(欧米諸国民ほど肉は大量に食べていないこと)、コーヒーなどもプラスの効果があったからと考えています。肉や乳製品の健康との関係を考えさせられる結果となりました。
では私たちはこれからどういう食事を摂っていくべきなのでしょうか、研究者には健康長寿の視点で、肉や乳製品の摂取のめやすなどをわかりやすく示してほしいものです。高齢者のアルブミン値が低下してる傾向などを考えるときどういう風に肉を食べ、乳製品をどういう風にうまく取り入れるかなども管理栄養士ともども国民に提示してほしい。
こうした生の情報で人々が混乱し、間違った判断をしないためにはそうしたフォローが必要かと思います。
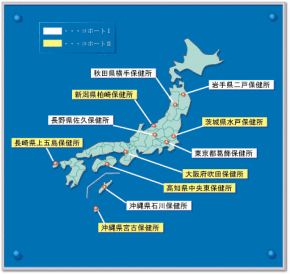
2017年5月29日月曜日
土壌は貴重な「資源」である~農地の洪水流失被害で思うこと~
昨年の北海道の富良野での台風被害は、その実態が科学的に詳しく紹介されてこなかったように思います。これはメディアの責任、特に科学ジャーナリストの責任があると考えています。
あまり報道されてこなかった事実として、この地が全国有数の「種イモ生産地」であって、実はここから種イモが日本中に供給されているという事実でしょうか。つまり富良野の被害は、富良野に留まらず、全国のイモ生産に大きな影響があったということです。特別に品質が問われる種イモは富良野のような寒冷地でないとうまく生産されないといいます。イモは私たちが日常口にしている食材ですが、そんな食材のことを何と無知であったかを教えてくれているようです。それにポテトチップスのような商品が、不足し生産ストップになっているということなどは詳しく報道されても、その背景を科学的視点で取材したものを目にすることはありません。
富良野での洪水被害関連であまり報道されてこなかった事実として、この地の貴重な「土壌」が大規模に流失し、奪われたことではないでしょうか。農家の方々が嘆いておられるように、農業の土=土壌は一朝一夕にできるものではありません。これは何代もかけ、有機肥料やたい肥で育て上げられた「財産=資源」なのです。イモの成長にふさわしい土壌は、何年もかけて「培われてきた」ものなのです。他に土地から土を運べばいいじゃないかと考えている人は多いと思いますが、イモ栽培の土壌は時間をかけて育て上げtられた「資源」なのです。土壌を研究している学者は、岩石が砕かれて植物が育ち、その有機物がまた分解されて土の粒をつくっていくという工程が、実に時間にかかる作業であることを明らかにしています。またそこに棲息する、ひとつかみで何億匹もいる微生物あるいは小動物などの働きは重要とされていますが、その99%はいまだどういう働きと作用をもった微生物かはわかっていないといいます。その地で生態系にさらされて作り出された「土壌」は、ほかのどの土地の土壌でもない、独特の個性と特性をもった土壌なのです。つまり現在、人がこうしした土壌を科学で作り出すことはできないのです。土壌というものがいかに貴重な「資源」であるかはこれで理解していただけると思います。復興にも影響するこうした科学的な事実こそもう少しきちっと伝えるべきではないでしょうか。写真:富良野観光協会

あまり報道されてこなかった事実として、この地が全国有数の「種イモ生産地」であって、実はここから種イモが日本中に供給されているという事実でしょうか。つまり富良野の被害は、富良野に留まらず、全国のイモ生産に大きな影響があったということです。特別に品質が問われる種イモは富良野のような寒冷地でないとうまく生産されないといいます。イモは私たちが日常口にしている食材ですが、そんな食材のことを何と無知であったかを教えてくれているようです。それにポテトチップスのような商品が、不足し生産ストップになっているということなどは詳しく報道されても、その背景を科学的視点で取材したものを目にすることはありません。
富良野での洪水被害関連であまり報道されてこなかった事実として、この地の貴重な「土壌」が大規模に流失し、奪われたことではないでしょうか。農家の方々が嘆いておられるように、農業の土=土壌は一朝一夕にできるものではありません。これは何代もかけ、有機肥料やたい肥で育て上げられた「財産=資源」なのです。イモの成長にふさわしい土壌は、何年もかけて「培われてきた」ものなのです。他に土地から土を運べばいいじゃないかと考えている人は多いと思いますが、イモ栽培の土壌は時間をかけて育て上げtられた「資源」なのです。土壌を研究している学者は、岩石が砕かれて植物が育ち、その有機物がまた分解されて土の粒をつくっていくという工程が、実に時間にかかる作業であることを明らかにしています。またそこに棲息する、ひとつかみで何億匹もいる微生物あるいは小動物などの働きは重要とされていますが、その99%はいまだどういう働きと作用をもった微生物かはわかっていないといいます。その地で生態系にさらされて作り出された「土壌」は、ほかのどの土地の土壌でもない、独特の個性と特性をもった土壌なのです。つまり現在、人がこうしした土壌を科学で作り出すことはできないのです。土壌というものがいかに貴重な「資源」であるかはこれで理解していただけると思います。復興にも影響するこうした科学的な事実こそもう少しきちっと伝えるべきではないでしょうか。写真:富良野観光協会
2017年5月24日水曜日
想像を超える「超巨大噴火」があらゆる生物の命を奪った!
2億5200万年前にあった史上最大の生物大量絶滅は、古生代が終わり、中生代の幕開けを知らせる地球史上のイベントとして記録されています(ペルム紀末大量絶滅 P/T境界)。このとき、生物の大量絶滅がなぜ起こったのか理由について様々な議論がなされていますが、確実にわかっているはこの時期、マントルオーバーターンの動きである「ホットプルーム」の活動が非常に活発になり、「超巨大噴火」が各地であったことです。ユーラシア大陸ではシベリア地域でこの大噴火の証拠を示す、玄武岩の広大な大地が見つかっています。玄武岩は、粘性の少ないマグマが固まってできたものです。
その面積は、700万平方キロメートル、日本の国土をはるかにしのぐ大きさの「熔岩大地」です。こうした超巨大噴火の遺跡ともいえる、玄武岩の大地はインドのデカン高原、アメリカのコロンビア台地などが有名ですが、現在の海洋の海底で見られる「海台」と呼ばれる広大な海底台地も実は、この玄武岩台地と考えられています。「洪水玄武岩」という名前がついています。この人類が経験したことにない規模の火山活動では、火山ガスが大気に大量にまかれ微粒子が全地球に漂い、太陽光を遮って異常気象を引き起こしました。また硫酸の雨が降り、環境はさらに悪化し気温も長期にわたり、数十度も下がったと考えられています。植物が消え、海も酸素欠乏状態となり、あらゆる生物は存在できないようになったものと思われます。
ここでいう「超巨大噴火」とは、数千万年から一憶年に一度あるという地球規模の噴火現象であり、私たちが知っているピナツボなどの噴火規模レベルではありません、もっともっと大規模な火山噴火が地球の歴史では繰り返し起こってきたのです。
<画像はシベリア洪水玄武岩 引用原文:Nature (2011-09-15) | doi: 10.1038/477285a >
2017年5月15日月曜日
いま「天然原子炉」の化石に学ぶべきもの
地球史のなかでひとつ謎めいた事実を挙げるとすれば、それは遠い昔にアフリカに「天然原子炉」が存在したという報告でしょうか。1972年ころ、ガボン共和国のオクロ鉱山でのフランス人研究者がある驚くべき事実をつきとめました。原子炉の燃料となる「ウラン」の同位体238と235の比率を調べたところ、他の地域と明らかに異なる比率を示したと言います。これはこの地で「核連鎖反応」が起こったことを科学的には示しています。では、なぜ核反応が生じたか、研究者たちはこれはきっと「自然の原子炉」が機能したのではと推量しました。「原子炉の化石」ではないかと考えたのです。
核連鎖反応には、ウラン235の十分な濃縮と周囲に水が存在することが必要とされます。水があることで連鎖反応は促進されるといいます。こうしたことは、可能性は論じられてきましたが、オクロのデータは計算によるとおよそ18億年前に実際に自然界で、核反応が起こったことを教えてくれています。その規模は、現在の商業用原子炉に比べ小さいものとされていますが、数十万年にわたり断続的に核連鎖反応が生じたものと考えられています。
この自然原子炉は、興味深い特異な地質ポイントというだけでなく、実は現代の私たちの社会的な問題と関連しています。原子力を使用することで必然的に常時発生する、「放射性廃棄物」をどう処分するかという問題です。最良の方策として検討されている、地中への埋設法でオクロは大きな情報を提供してくれるのです。例えば、揮発性の核生成物、カドミウムとかセシウムなどは大部分失われているのに対して、ウランやトリウムは18億年経ってもそのまま残っていることなどが事実として分かっています。オクロのことをもっと論じていくべきではないでしょうか。核廃棄物の処理法については、いまや誰も真剣に議論しないようになっていますが、こうしている間も、核のゴミはこの狭い国土に蓄積され続けています。
核連鎖反応には、ウラン235の十分な濃縮と周囲に水が存在することが必要とされます。水があることで連鎖反応は促進されるといいます。こうしたことは、可能性は論じられてきましたが、オクロのデータは計算によるとおよそ18億年前に実際に自然界で、核反応が起こったことを教えてくれています。その規模は、現在の商業用原子炉に比べ小さいものとされていますが、数十万年にわたり断続的に核連鎖反応が生じたものと考えられています。
この自然原子炉は、興味深い特異な地質ポイントというだけでなく、実は現代の私たちの社会的な問題と関連しています。原子力を使用することで必然的に常時発生する、「放射性廃棄物」をどう処分するかという問題です。最良の方策として検討されている、地中への埋設法でオクロは大きな情報を提供してくれるのです。例えば、揮発性の核生成物、カドミウムとかセシウムなどは大部分失われているのに対して、ウランやトリウムは18億年経ってもそのまま残っていることなどが事実として分かっています。オクロのことをもっと論じていくべきではないでしょうか。核廃棄物の処理法については、いまや誰も真剣に議論しないようになっていますが、こうしている間も、核のゴミはこの狭い国土に蓄積され続けています。
2017年4月11日火曜日
雲の成因は「宇宙線」という説!宇宙物理学の進展
わかっているようでわかっていないことはあります。例えば地球を覆う「雲」がその面積があまり変わらないことが知られていますが、そうしたことがどういうメカニズムなのか詳しくはわかっていませんでした。
20年ほど前に出されて学説があります。デンマークの宇宙物理学者のヘンリク・スベンスマルク博士が説いた雲の成因を宇宙に求める新説です。地球には宇宙空間から、常に「宇宙線」すなわち陽子などの高エネルギー粒子が降り注いでいますが、この宇宙線が大気圏の水蒸気(飽和水蒸気)に刺激を与えると、大気の小さなチリを核として水の微粒子が生まれ、それが雲の成因となるという説です。この説によると太陽の磁場がなんらかの理由で弱くなると、バリアー効果が弱くなり太陽系に注ぐ宇宙線の量が増え、結果として地球ではより多くの「雲」発生することとなるといいます。
過去をさかのぼってこうしたことが証明できるか、調べているようですが地球環境の温暖化、あるいは寒冷化は実は宇宙からやってくる宇宙線量に左右されているという証拠も集まっているようです。6500万年前のあの恐竜たちの大絶滅もこの宇宙線量の大規模な変動があったのではないか、宇宙の環境変化に原因をさぐる考え方も登場しています。たしかに考えてみると地球といっても銀河のなかで周囲の環境変動から独立しているわけではなくはずで、逆に宇宙の環境に大きな影響を受けて変化、進化してきたのは当然のことともいえるかもしれません。
宇宙の大規模な構造や、ダークマター、エネルギーの実態がもっとつまびらかになれば地球や生物のこれまでの進化、変貌は新たな解釈が進むのかもしれません。
20年ほど前に出されて学説があります。デンマークの宇宙物理学者のヘンリク・スベンスマルク博士が説いた雲の成因を宇宙に求める新説です。地球には宇宙空間から、常に「宇宙線」すなわち陽子などの高エネルギー粒子が降り注いでいますが、この宇宙線が大気圏の水蒸気(飽和水蒸気)に刺激を与えると、大気の小さなチリを核として水の微粒子が生まれ、それが雲の成因となるという説です。この説によると太陽の磁場がなんらかの理由で弱くなると、バリアー効果が弱くなり太陽系に注ぐ宇宙線の量が増え、結果として地球ではより多くの「雲」発生することとなるといいます。
過去をさかのぼってこうしたことが証明できるか、調べているようですが地球環境の温暖化、あるいは寒冷化は実は宇宙からやってくる宇宙線量に左右されているという証拠も集まっているようです。6500万年前のあの恐竜たちの大絶滅もこの宇宙線量の大規模な変動があったのではないか、宇宙の環境変化に原因をさぐる考え方も登場しています。たしかに考えてみると地球といっても銀河のなかで周囲の環境変動から独立しているわけではなくはずで、逆に宇宙の環境に大きな影響を受けて変化、進化してきたのは当然のことともいえるかもしれません。
宇宙の大規模な構造や、ダークマター、エネルギーの実態がもっとつまびらかになれば地球や生物のこれまでの進化、変貌は新たな解釈が進むのかもしれません。
2017年4月3日月曜日
生物進化の大いなる謎~ヘビに擬態する幼虫の不思議~
ヘビに擬態するイモムシをご覧になったことがありますか。擬態する生物は数多く存在していますが、この見事なヘビに似せた姿には感服せざるを得ません。この幼虫は、アルゼンチンのサンタフェでとある家のお庭で見つかったものだそうですが、眼は瞬きをするような動作をすることができると伝えられています。実際のヘビは瞬きをしないのですが。
無防備な幼虫が、我が身を守る術として、野鳥の餌食にならないようにとこうした格好になったというのが生物学的な解釈ですが、ではどうしてこの姿が防御になるかを知っているのかは説明できません。現代の進化論では、たまたま変異した姿が、有効であったので生き残り、それが形態変化を促したと言うのでしょうがどうもそれでは納得できません。枯れ葉に似せたカラダを作って、周囲の環境に溶け込むといった擬態ではそういう変異種が積み重なって生き残ったという考えかたで、なんとなく理解はできそうですが、このイモムシ(幼虫)もっと積極的に、何かに似せるという進化が行なわれています。天敵の怖がるものに似せるということですが、では誰がそれを理解していたのでしょうか。誰かが教えたとは考えられません。擬態には何か未知な生物の能力が秘められていると感じさせるものがあります。
ヘビに擬態するスズメガの一種の幼虫。(JOHN CANCALOSI/NATIONAL GEOGRAPHIC CREATIVE)
2017年2月21日火曜日
なぜ地球に磁場があるのか~マントルオーバーターンの発見~
地球に磁場が存在しているのは当たり前にように思っていますが、たとえば金星には磁場はなく、どの惑星でも磁場があるわけではないのです。磁場が生まれるためには、惑星の「核」が流動的で、対流を起こしている必要があります。地球では、金属からなる「核」の上部の部分(外核)は、
鉄やニッケルが解けた液化した金属でできています。この液体が対流運動を起こすことで、いわゆるダイナモ効果を起こし、地球には地磁気が生まれます。この磁場により、地球の周りににいわゆる磁気バリアが誕生し、有害な放射線、太陽風などから地球の生物は守られているるのです。オーロラが、両極で見えるのも地磁気が存在があるからです。
地球にもはじめから地磁気があったわけではなく、27億年ほど前にマントルが大きく対流する、いえあゆる「マントルオーバーターン」という現象が生じてからだという。地球を覆う11枚のプレートは大陸の周辺で沈み込みますが、それは深さ670キロあたりにたまります(プレートの墓場といわれています)。この冷たいプレートの成れの果てはある時、崩れ落ちるようにマントル内部へと沈んでいくことがわかってきました。これは「コールドプルーム」と呼ばれる、壮大な岩石の流れで、外核の表面あたりまでしれは達します。このコールドプルームが到達した、外核分部は冷却されますが、このことが外核分部に温度差を生み、液体の外核に対流を生じさせていると考えられています。壮大な温度の流れと物質の流転です。これらの現象は偶然のことかも知れませんが地上に生き物が生存する条件を整える結果となりました。
鉄やニッケルが解けた液化した金属でできています。この液体が対流運動を起こすことで、いわゆるダイナモ効果を起こし、地球には地磁気が生まれます。この磁場により、地球の周りににいわゆる磁気バリアが誕生し、有害な放射線、太陽風などから地球の生物は守られているるのです。オーロラが、両極で見えるのも地磁気が存在があるからです。
地球にもはじめから地磁気があったわけではなく、27億年ほど前にマントルが大きく対流する、いえあゆる「マントルオーバーターン」という現象が生じてからだという。地球を覆う11枚のプレートは大陸の周辺で沈み込みますが、それは深さ670キロあたりにたまります(プレートの墓場といわれています)。この冷たいプレートの成れの果てはある時、崩れ落ちるようにマントル内部へと沈んでいくことがわかってきました。これは「コールドプルーム」と呼ばれる、壮大な岩石の流れで、外核の表面あたりまでしれは達します。このコールドプルームが到達した、外核分部は冷却されますが、このことが外核分部に温度差を生み、液体の外核に対流を生じさせていると考えられています。壮大な温度の流れと物質の流転です。これらの現象は偶然のことかも知れませんが地上に生き物が生存する条件を整える結果となりました。
2017年1月26日木曜日
潰さないで!「准高齢者」の議論~世界に発信するニッポン型シニア活躍社会~
本当の「高齢者」は75歳からで、65歳から74歳までは「准高齢者」と位置づけようという議論があります。高齢社会は、いまや途上国も年齢構成は、次第に先進国を追いかけていて、全人類的な課題となりつつあります。国民総活躍社会というのであれば、日本は率先してこのことを実現しなければなりません。現在の日本の企業は、65歳まではなんらかの採用継続を試みていますが、65歳を超えると役員は別にして、まったく関心がなくなり会社に対しては価値のない人として扱われます。企業というのはそういうものでしょうか。准高齢者となる方もそのことを覚悟して、退職を迎えるべきですが、突然の帰属の消滅という実感を持つ方も多いと思われます。一方実際に、准高齢者はとても元気な方が多いというのが現実で、この世代のスキルや経験を社会に還元することは、少子高齢の状況に喝を入れ、活性化させる可能性を秘めていると思われます。問題は、准高齢者が活躍できる環境をどう作っていくかだと専門家は指摘しています。また若者とは異なる准高齢者の体調に合わせた労働環境や、医療制度、報酬、社会保障等の構築も求められます。またそれでも准高齢者世代は、健康状態は一人ひとり異なるはずです。本当にリタイヤしたいと望む方も大勢いるかもしれません。内閣府調査のデータでは、働ける間はいつまでも働きたいという意見の方がおよそ29%に登るといいます。またこうした議論をすぐに年金支給開始年齢の引き上げ論と結びつけて、政府に資する偽の議論だと歪曲化し、陥れる人たちがいます。議論は議論で皆で考える時期が来ていると思います。実際、科学的な調査から、この10年間で65歳以上の「心身の機能」は、なんと5歳~10歳は確実に若返っているという現実もあるのです。いまの65歳はかつての55歳の体力と精神を備えているといえるのです。これからこの准高齢者世代をどのように考え、社会的に位置づけていくのか、この重要な議論を潰さないでほしい。来たるべき幸せなシニアも活躍する社会システムをどう築いていくのか、日本人の知恵がいま試されています。
登録:
投稿 (Atom)
